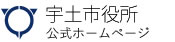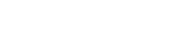今朝の網津川です。水量も少なく穏やかです。
川沿いに立地する網津小は水防対策が必要な学校です。
この写真は,平成28年6月21日の写真です。
熊本地震の約1ヶ月余後です。網津川が氾濫し,校庭に土砂が流れ込み,当時の職員が総出で土砂を掻き出す作業に取り組んでいます。この日は休校になったそうです。
梅雨に入る直前ですが,6日土曜日に児童の引き渡し訓練をさせていただきます。保護者の皆様,お世話になりますm(_ _)m
さて,今日のお気に入りの写真は,

2年生が生活科の学習でミニトマトやパプリカを栽培しています。
1・2年生に「生活科」という教科が登場したのは平成になってからです。子どもたちの日常生活の中に,生産活動や遊び,自然体験が乏しくなってきたので,学校教育の中でそれらを補おうという趣旨でした。
哲学者の内田樹さんの言葉です。
「今の子どもたちと今から30年前の子どもたちの間の一番大きな違いは何かというと,それは社会関係に入っていく時に,労働から入ったか,消費から入ったかの違いだと思います。・・・・社会的能力のない幼児が成長していく過程で,社会的な承認を獲得するために何をしたかというと,まず家事労働したわけです。ご飯を食べた後,お茶碗を台所まで持っていくとか,庭掃除するとか,打ち水をするとか,犬を散歩に連れていくとか,父親の靴を磨くとか・・・・・当然『ありがとう』とか『よくやったね』とかほめてくれる。子どもはそれが嬉しいし,誇らしい。」(『下流志向』講談社文庫より)
今の子どもたちは,幼い頃から“お客様”扱いに慣れています。どんなに小さい子どもでも,お店でお金を払えば立派なお客様としてサービスを受けられる。対人関係において,まず消費者感覚を身につけます。この感覚が強い子どもは,親が「ちょっと手伝って」とお願いをすると,「いいよ,いくらくれるの?」等と返答します。また,「今度のテスト,頑張ってね」と励ますと,「うん,100点取ったら何を買ってくれるの?」等とも言います。本人には悪気はないのです。自分は常に消費者だと思っているので,そういう要求をするのです。
だから,学校教育では,“消費”ではなく,“生産”に重きをおきます。
植物や作物を無償で植えるけれど,花が咲く喜びや収穫の喜び,皆と協働して育てた達成感を味わう・・・・等々,2年生の生産活動の狙いはそこにあります。
今朝,朝活動の後,6年生が通路にはじき飛ばされた砂利石を拾い,元の場所へ戻してくれていました。
正に,“生産” です。
自らの無償の作業の結果,人が喜んでくれる,人の役に立てたと喜びを感じることができる。お金では決して買えない経験をしています。
「損か?得か?」(消費) ではなく, 「人の役に立つか? 人が喜ぶか?」(生産) で考えることのできる子どもを育てたいと思っています。
保護者の皆様,子どもの家事労働の無償化,子どもの成績向上の脱ご褒美化を進めましょう(^^)/