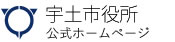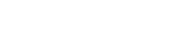本日〔9月19日(水)〕の子どもたちの活動の様子を紹介します。
午前中は、ばら組(年中組)の研究保育を行いました。ねらいは、忍者について知り、興味関心を持ったり、友達と一緒に忍者になりきって表現することを楽しんだりすることです。
まずは、一つ目の活動として、忍者になって、一本橋やブロックの上を渡り、水の中(実際は青色のマット)を進むという活動をしました。子どもたちは、一本橋やブロックの上を手を広げたりしてバランスを取りながら、楽しそうに進んでいました。水の中では、腹ばいや仰向けになって手や足を使って進んだり、前回りをしたりしながら楽しそうに進んでいました。
二つ目の活動では、2人組になって、同じ動きを楽しむというものです。まず、職員2人が例を示すために、ゴリラの動きをしました。職員が、違う動きや同じ動きをするのを見て、子どもたちは同じ動きと違う動きについて理解することができました。(職員の動きの上手さに、思わず感心してしまいました。)子どもたちは、竜巻やネコ、ウサギなどの動きを上手に表現していました。中には、鏡を2人で見ながら練習する子どもたちの姿が見られ、すごいなあと思いました。(小学校でもタブレットを使って、体育や音楽、図工、家庭科などの授業で活動の様子をお互いに録画し、互いに見合ったりしています。自分の活動の様子を自分で観察することで、子どもたちはよくできている点や直したほうが良い点に自分で気づき、技能の向上につなげています。)
うめ組(年長組)は、大太鼓教室を市民会館で行いました。
まず、講師の先生が自己紹介をされ、桶胴太鼓を叩かれました。テンポよく、軽く早く叩かれたり、力強くゆっくりと叩かれたり、バチを変えて叩かれたりしました。叩き方やバチを変えることで、音の大きさや音色が変わったりすることを学びました。また、締め胴太鼓の綱の締め方を変えることで、音の高さが変わることも学びました。
次に、私たち職員3人と講師の先生で、4つの楽器(オーシャンドラム、シンギングボウル、ティンシャ、篠笛)を使って民謡を演奏しました。子どもたちは、民謡の曲はだれも知りませんが、「懐かしい」という言葉を発する姿が何人も見られました。とても不思議なことだと思いました。(民謡が持つ人の心に訴える何か不思議な力があるのでしょうか?)
次に、大太鼓の歴史や値段(一番大きな太鼓は数千万円するそうです)などの話もされました。
後半は、子どもたちが実際に太鼓を叩きました。講師の先生が先に叩かれて、それを真似して叩いたり、自分の好きなリズムで叩いたりしました。1時間ほどの活動で、子どもたちも十分に満足できたようです。子どもたちからは、次のような感想が聞かれました。
・太鼓の音が大きくて、胸がドンドンした。
・太鼓の音が大きくてびっくりした。
・太鼓の音が大きくて楽しかった。
子どもたちにとって、とても有意義な活動になったようです。