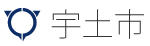法定軽減制度(申請不要)
世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)と同一世帯内の国民健康保険被保険者の前年の世帯の総所得金額が、条例により定められた基準(下表参照)を下回る世帯は、均等割、平等割の7割、5割又は2割を軽減します。
| 前年の世帯の総所得金額の合計額 | 軽減割合 |
|---|---|
| 430,000円+(100,000円×給与所得者等の数-1)以下 | 7割 |
| 430,000円+(295,000円×被保険者数と特定同一世帯所属者数) +(100,000円×給与所得者等の数-1)以下 | 5割 |
| 430,000円+(545,000円×被保険者数と特定同一世帯所属者数) +(100,000円×給与所得者等の数-1)以下 | 2割 |
※特定同一世帯所属者:同一世帯の中で、国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した人
※給与所得者等とは、給与所得もしくは公的年金等の支給を受ける人
特定世帯(申請不要)
これまで国保被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、同一世帯の他の国保被保険者が1人だけとなった世帯を「特定世帯」といいます。この場合、国民健康保険税の「医療給付費分」と「後期高齢者支援金分」の平等割額が最大で5年間は半額になり、その後は最大で3年間、1/4軽減(3/4を課税)されます。(世帯構成が変わると対象外になる場合があります。)
旧被扶養者(申請必要)
これまで被用者保険(会社の社会保険や共済組合等をいい、国保組合を除きます。)の被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、被用者保険の被扶養者から国保被保険者となった65歳以上の方を「旧被扶養者」といいます。
「旧被扶養者」の方は、所得割が当分の間かかりません。また、均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで半額(※)となります。さらに、旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割額も資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで半額(※)となります。
※「7割軽減」、「5割軽減」の対象となる世帯を除きます。
非自発的失業者にかかる国民健康保険税の軽減制度(申請必要)
非自発的失業(離職)により国民健康保険へ加入する方の国民健康保険税について、申請により失業(離職)から一定の期間、前年の給与所得を30/100として算定し賦課することにより、国民健康保険税を軽減します。ただし、世帯に属するその他の被保険者の所得は、通常の額を算定します。給与所得以外は、100/100として算定します。
| 離職日 | 平成21年3月31日以降に失業した人 |
|---|---|
| 離職時の年齢 | 失業時点で65歳未満 の人 |
| 離職理由コード | 雇用保険受給資格者証の離職理由欄に記載の離職理由コードが 「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」 のいずれかに該当する人 |
| 軽減の対象となる期間 | 離職年月日の翌日の属する月から翌年度末まで (最大2年間) |
| 軽減内容 | 対象者の前年の給与所得を30/100として保険税を計算します |
| 申請時の必要書類 | 国民健康保険証、雇用保険受給資格者証(※) |
未就学児に係る国民健康保険税の減額(申請不要)
子育て世帯の経済的負担軽減の観点より、令和4年度から未就学児に係る国民健康保険税の均等割額について1/2が減額されます。
世帯の所得により軽減措置(2割、5割、7割)が適用されている場合は、さらに未就学児に係る均等割額を1/2減額します。例えば、2割の所得軽減措置が適用されている世帯における未就学児の場合、残り8割の1/2を減額することから、全体で6割軽減となります。
世帯の総所得金額等の合計に応じた軽減措置についてはこちらをご覧ください。
| 所得軽減世帯 | 減額割合 | |
|---|---|---|
令和3年度 | 令和4年度以降 | |
| 軽減なし世帯 | 軽減なし | 5割 |
| 2割軽減世帯 | 2割 | 6割 |
| 5割軽減世帯 | 5割 | 7.5割 |
| 7割軽減世帯 | 7割 | 8.5割 |
災害により住宅・家財の損害を受けた場合(申請必要)
災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除いた額)が、住宅又は家財の価格の10分の3以上で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下の場合は減免されます。
全壊、半壊等の場合(損害程度:10分の5以上)
合計所得金額 | 減免割合 |
|---|---|
| 500万円以下 | 全部 |
| 750万円以下 | 2分の1 |
| 750万円以上 | 4分の1 |
一部損壊、床上浸水等の場合(損害程度:10分の3以上10分の5未満)
合計所得金額 | 減免割合 |
|---|---|
| 500万円以下 | 2分の1 |
| 750万円以下 | 4分の1 |
| 750万円以上 | 8分の1 |
必要書類
・罹災証明書等、被災状況が確認できるもの
・保険金、損害賠償金等を確認できるもの
・居住する持家の面積や価値、所有する家財の価値が分かる書類
災害により農作物の損害を受けた場合(申請必要)
冷害、凍霜害、干害等により、農作物に被害を受けた場合、農作物の減収による損失額(※1)が平年の収入額の10分の3以上、前年中の合計所得金額が1,000万円以下(※2)で、前年中の農業所得金額(※3)が次のいずれかの区分に該当する場合は減免されます。
(※1)農作物の減少額から農作物共済金額を除いた額
(※2)合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く
(※3)合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た金額
合計所得金額 | 減免の割合 |
|---|---|
| 300万円以下 | 全部 |
| 400万円以下 | 10分の8 |
| 550万円以下 | 10分の6 |
| 750万円以下 | 10分の4 |
| 750万円以上 | 10分の2 |
必要書類
・被災状況が確認できるもの
・農業共済の支払証明書等
事業廃止等で所得が激減した場合(申請必要)
「解雇、倒産等による退職若しくは失業又は事業の休廃止」等の事由により、同一世帯の当該年中の合計所得金額の見積額が、皆無になる場合は所得割額が減免されます。
前年中の合計所得金額 | 減免の割合 |
|---|---|
| 150万円以下 | 10分の7 |
| 150万円以上300万円以下 | 10分の6 |
| 300万円以上450万円以下 | 10分の4 |
| 450万円以上600万円以下 | 10分の3 |
必要書類
・給与明細書、通帳
・税務署への廃業・休業届(自営業の場合)
・雇用保険受給資格者証(解雇等の場合)
・診断書・入院証明書(傷病の場合)等
収監されていた場合(申請必要)
刑事施設等に収監された場合は、収監された月から退所した前月までの国保税が全額減免されます。
必要書類
・在所証明書
生活保護になった場合(申請必要)
生活保護を受給するに至った場合は、保護開始日以後の納期未到来分の国保税が全額減免されます。
必要書類
・生活保護受給証明書
産前産後期間に係る国民健康保険税の減額(申請必要)
国民健康保険法施行令の改正により、子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援等の観点から、令和6年1月より国民健康保険に加入している人が出産した場合、産前産後期間にかかる所得割額及び均等割額を免除します。
対象者
国民健康保険の被保険者で令和5年11月1日以降に出産する(した)人が対象です。
※出産とは妊娠85日(4か月)以降の出産(死産・流産・人工妊娠中絶含む)をいいます。
届出期間
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
※これより前に届出することはできませんので、ご注意ください。
国民健康保険の免除期間
●その年度に収める国民健康保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月の4か月相当分が減額されます。
| 3か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 出産予定月 | 1か月後 | 2か月後 | 3か月後 | |
| 単胎の人 | 対象期間 | ||||||
| 多胎の人 | 対象期間 | ||||||
※産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が年税額から減額されます。産前産後期間の国民健康保険税が0円になるとは限りません。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。
必要書類
1.産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(税務課窓口にて配布)
2.母子健康手帳など
3.届出者の本人確認書類(マイナンバー、運転免許証など)