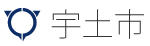子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)の定期接種について
ヒトパピローマウイルス(HPV)は、子宮頸がんを始め多くの病気の原因とされています。HPV感染症を防ぐためのワクチン(HPVワクチン)は、平成25年4月1日から定期予防接種となりました。しかし、このワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛等の副反応が報告されたことから、同年6月14日に、国から市町村等へ、国民に適切な情報提供ができるまでの間、積極的な勧奨を控えるよう通知がなされました。
その後、HPVワクチンの有効性および安全性に関する評価、接種後に生じた症状への対応、情報提供の取組等について議論が行われ、ワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ることが認められました。
その結果、HPVワクチンの積極的勧奨を差し控えている状態を終了させることが妥当と判断され、令和3年11月26日に、国から市町村等への通知により、令和4年度から対象者へ勧奨を再開することになりました。
宇土市では、標準接種年齢となる女子へ通知を発送します。
また、積極的勧奨の差控えにより、接種機会を逃した方に対してキャッチアップ接種を実施します。
接種対象者(接種当日に宇土市に住民票のある下記の方)
●小学校6年生~高校1年生相当の女性(標準接種年齢は中学1年生)
●キャッチアップ対象者(※下記をご覧ください)
キャッチアップ対象者
令和7年3月31日まで
平成9年4月2日生まれ~平成20年4月1日生まれの女性(キャッチアップ対象者)で、過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない方。
令和7年4月1日以降~令和8年3月31日まで
下記の要件をすべて満たす方が対象となります。
・接種時に宇土市に住民票があること(転出された場合は転出先の市町村に相談してください)
・令和6年度キャッチアップ接種対象者(平成9年度~平成19年度生まれの女子)もしくは、平成20年度生まれの女子
・令和4年4月1日~令和7年3月31日までの間にHPVワクチンを1回以上接種した方
※過去に接種したワクチンの情報(ワクチンの種類や接種時期)については、母子健康手帳や予防接種済証等でご確認ください。
※転出された場合は宇土市の予診票は使えません。転出先の市町村に接種前に必ず相談されてください。事前手続きを必要とする市町村もあり、手続きをしていないと自費(30,100円程度/回)となることもあります。
HPVワクチンの種類
公費で受けられるHPVワクチンは、防ぐことができるHPVの種類(型)によって、2価ワクチン(サーバリックス)、4価ワクチン(ガーダシル)、9価ワクチン(シルガード9)の3種類あります。
- 「ガーダシル」「サーバリックス」と「シルガード9」は、異なるワクチンを接種した場合の安全性・有効性などが十分に分かっていないため、原則同じワクチンを接種することになっています。
- ワクチンの種類の取り扱いは医療機関によって異なりますので、必ず事前にご確認ください。
2価または4価ワクチンと9価ワクチンとの交互接種について
原則として同じ種類のワクチンを接種することをお勧めしますが、医師と相談のうえ、途中からシルガード9に変更し、残りの接種を完了させることができます。この場合も定期接種の対象となります。また、キャッチアップ接種の対象の方も、途中からシルガード9に変更し、残りの接種を完了させることができます(※)。
(※)異なる種類のワクチンを接種した場合の効果と安全性についてのデータは限られています。
接種スケジュール
3種類いずれも、1年以内に接種を終えることが望ましいとされています。
| ワクチン名 | 接種回数 | 接種間隔 | |
|---|---|---|---|
| 2回目 | 3回目 | ||
| サーバリックス (2価ワクチン) | 3回 | 1回目から1か月 | 1回目から6か月 |
| ガーダシル (4価ワクチン) | 3回 | 1回目から2か月 | |
| シルガード (9価ワクチン) | 3回 | 1回目から2か月 | |
| 2回※ | 1回目から6か月 | - | |
※15歳になるまでに1回目の接種を行った方は、2回での接種で完了することが可能
予防接種の効果について
公費で受けられるHPVワクチンは、子宮頸がん全体の50~70%の原因とされるヒトパピローマウイルス(HPV)16型及び18型の感染を防ぐことができます。
HPVワクチンの接種により、感染予防効果を示す抗体は少なくとも12年は維持される可能性があることが、これまでの研究で分かっています。
また、前がん病変や子宮頸がんそのものを予防する効果があることも分かってきています。
HPVワクチンの予防接種を1万人が受けると、受けなければ子宮頸がんになっていた約70人ががんにならなくてすみ、約20人の命が助かると試算されています。
ただし、HPVワクチンの予防接種を受けた場合でも、全ての発がん性HPV感染を防ぐことはできないため、20歳になったら、子宮頸がんを早期発見するため、子宮頸がん検診を定期的に受けることが重要です。
予診票の発行方法
次のいずれかの方法で申込みをしてください。
窓口へ来所する
母子健康手帳と申請者の身分証明書を持参の上、宇土市健康づくり課にお越しください。
- 電子申請で申請し、窓口へ来所
次の申請フォームから事前に申請されておくと、窓口来所時は受け取りのみになります。⇒【窓口受け取り用】申請フォームはこちら
- 電子申請で申請し、郵送で発行
次の申請フォームから申し込みください。⇒【郵送用】申請フォームはこちら
※令和4年4月1日~令和7年3月31日までの間にHPVワクチンを1回以上接種した方 については、現在お持ちの予診票で接種することが可能です。
※令和6年11月以降に予診票を依頼された方については、発行を行わなかった回数の予診票を、3月下旬に郵送する予定です。予診票が届かない場合は、健康づくり課母子保健係(0964-27-4428)にお問い合わせください。
自費で接種した方について
子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)の積極的な接種の勧奨を差し控えている間(~令和4年3月31日)に、接種の機会を逃した方で、既に自費で接種を受けた方に対して接種費用の償還払い(払い戻し)を実施します。
詳しくは下をご覧ください。
予防接種予診票再発行手続き、市外接種手続きについて
市外接種手続きは、予防接種する前の事前の申請が必要になります。詳しくは子どもの予防接種(サイト内リンク)をご覧ください。
関連ホームページ
- ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~(厚生労働省)
- HPVワクチンに関するQ&A(厚生労働省)
- ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種を逃した方へ~キャッチアップ接種のご案内~(厚生労働省)