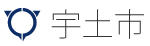江戸時代の宇土藩主・細川家がどのような正月を過ごしていたのか?江戸時代中頃の宝暦5(1755)年に書かれた日記から正月三が日の行事を紹介します。
元日
この年の元日(旧暦)は、朝から雪が舞うほど寒い1日でした。現在の暦では2月中旬にあたります。まず、藩主・興文(おきのり)は、起床して身支度を整えると、決まった作法に従って神仏に祈りを捧げ、決められた朝食を食べます。当日の日記には「年頭の儀式が滞りなく済む」とだけ記されています。その後、朝五つ半時(午前9時)から屋敷の広間で家臣たちから年賀の挨拶を受けます。この屋敷は現在の教育委員会(新小路町)付近にあった細川家屋敷です。家臣たちの挨拶が終わると、「御流頂戴(おながれちょうだい)」という儀式に移ります。初めに藩主が土器(からわけ)と呼ばれる盃で酒を飲み、家臣たちも土器で藩主と同じ酒を飲む儀式です。これは、藩主と家臣が同じ酒を飲むことで、一味同心する(心を一つにする)という意味合いがありました。身分が低い家臣は、「御流頂戴」には参加せず、代わりに藩主から熨斗(のし:細長く切ったアワビを乾燥させ、紙で包んだもの)が下賜されます。午後には、役替(異動)があった家臣や新規に取り立てられた家臣、宇土町の代表者である別当(べっとう:町人の意味)が、藩主に対して御礼の挨拶を行います。
2日
2日は、朝五つ半時(午前9時)から藩主と主だった家臣たちが、三宮社(現在の西岡神宮)に初詣に出かけます。ここでは金百疋(ひき)を神前に奉納していますが、「疋」とは、贈答用の金貨を数える時の単位で、現在の価値にすると1~2万円位でしょうか。夕方七つ時(午後4時)からは、担当の家臣が細川家屋敷の床の間に具足餅と鏡餅を供えます。具足餅とは、先祖伝来の具足(鎧)を飾り、その前に備えた餅のことです。この餅は11日の夕方まで飾られ、その夜家臣たちに振舞われています。
3日
3日は、肥後本藩の藩主に新年の祝儀として、太刀1本と馬代として銀を進呈しています。これは前日から熊本城下に赴いている藩主代理の家臣が届けています。朝五つ半時(午前9時)からは、藩主をはじめ、家臣やその子供たちが屋敷内の馬場で馬の乗り初めを行います。乗り初めの後は、馬の洗い初めも行われ、藩主もその様子を見物しています。夜には、藩主と家臣たちによる御謡い初めの会が開かれています。これは大名や武家の嗜みの一つであった謡曲(ようきょく)の謡い始めの儀式で、高砂・養老・老松という正月らしいめでたい曲が謡われています。閉会後は酒宴が催され、ようやく正月三が日が終了します。
江戸での正月
しかし、藩主は毎年宇土で正月を迎えるわけではありません。江戸時代は参勤交代という制度があり、藩主は1年おきに江戸と国元(宇土)で過ごします。江戸の宇土藩上屋敷は、現在の国会議事堂敷地内にありました。藩主が正月を江戸で過ごす場合、宇土藩主をはじめ外様大名は正月2日目早朝から江戸城に登城して、将軍に年賀の挨拶を述べ、太刀1本と馬1匹を献上することが通例となっています。太刀や馬を江戸城まで持って行くのは大変ですから、実際には目録を渡しています。返礼として大名たちには、「御流頂戴」時服(じふく)と呼ばれる小袖が下賜されています。厳粛な雰囲気の中、将軍に対面する大名たちの緊張した様子が想像されます。
このように正月三が日は、重要な行事が目白押しで、大名とはいえ「寝正月」というわけにはいかなかったようです。むしろ1年でもっとも慌ただしく、何かと気を遣う3日間だったのかもしれません。
正月に江戸城内でおこなわれた「御流頂戴」の様子