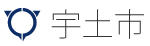第8代横綱「不知火型土俵入り」
 江戸時代、相撲界に宇土市出身の名横綱がいました。「不知火型土俵入り」の創始者、第8代横綱“不知火諾右衛門”です。
江戸時代、相撲界に宇土市出身の名横綱がいました。「不知火型土俵入り」の創始者、第8代横綱“不知火諾右衛門”です。
諾右衛門は幼名を近久信次といい、享和元年(1801年)宇土市栗崎町に生まれました。子供の頃から宮相撲をとり、力持ちで有名であったといいます。造り酒屋で働いていた時、近くで火事があり、酒蔵の樽を一人で運び出したというエピソードもあります。
文政6年、大阪相撲の湊由良右衛門に入門して大関まで昇進し、後に、相撲の本場であった江戸相撲にも挑戦して、天保11年(1840年)には横綱の免許を与えられました。3年後、江戸城内で将軍徳川家慶の上覧相撲が催され、この時の土俵入り(不知火型)を描いた綿絵が残されています。諾右衛門の体格は、身長約175cm、体重約135kgという当時としては堂々たるものであったようです。
天保15年に引退し、大阪において湊由良右衛門を継いで大阪相撲の頭取となり、後進の育成に尽力しました。嘉永7年に54歳で他界し、分骨された墓が故郷である栗崎町の小高い丘の中腹にひっそりと立っています。