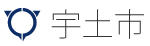ディスレクシアを知っていますか?
ディスレクシアとは学習障害(LD)の一つとされます。学習障害の中でも読み書き能力に困難を示す障がいです。そのことによって学業不振が現れたり、二次的な学校不適応などが生じる疾患です。ケガや病気などで脳の言語をつかさどる部分が損傷し読み書きが難しくなる「失語症」とは異なり、生まれつきの特性です。
※学習障害(LD)とは、基本的には全般的な知的発達に遅れはありませんが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指すものです。
ディスレクシアの初期症状
| 読むことが苦手 | ・幼児期には文字に興味がなく、覚えようとしない ・文字を一つ一つ拾って読む(逐次読み) ・語あるいは文節の途中で区切ってしまう ・読んでいるところを確認するように指で押さえながら読む ・文字間や行間を狭くするとさらに読みにくくなる ・初期には音読よりも黙読が苦手である ・一度、音読して内容理解ができると二回目の読みは比較的スムーズになる ・文末などは適当に自分で変えて読んでしまう ・本を読んでいるとすぐに疲れる |
| 書くことが苦手 | ・促音(「がっこう」の「っ」)、撥音(「とんでもない」の「ん」)、 二重母音(「おかあさん」の「かあ」)など特殊音節の誤りが多い 「わ」と「は」、「お」と「を」のように耳で聞くと同じ音(オン)の表記に誤りが多い ・「め」と「ぬ」、「わ」と「ね」、「雷」と「雪」のように形態的に似ている文字の誤り が多い ・画数の多い漢字に誤りが多い |
気づくことが大事
ディスレクシアは、本人の努力不足や知的発達の遅れと誤解され見過ごされやすい障がいです。症状は人それぞれであるため困っていることを本人に聞き、負担を軽減できる支援を学校や家庭で工夫していくことが大切になります。
学校におけるディスレクシアの効果的支援
1 宿題の問題文や教科書の漢字にふりがなを振る
2 黒板を写真にとって記録する
3 ノートの代わりにタブレット端末に入力する
4 宿題の量などを話し合って調整する
5 漢字の覚え方を工夫する
6 試験時間を延長する
上記以外でも宇土市では、デジタル教科書を利用し、ディスレクシアの児童生徒に対し、教科書の漢字にふりがなを振ったものを印刷し対応を行っています。また、児童生徒一人一台のタブレットを配布し、児童生徒の状況に応じて読み上げ機能を使ったり、タブレットに入力したりする対応を行っています。宿題の量の調整等ほかの項目についても状況に応じて対応を行っています。
学校と家庭の連携が大切
教育面、生活面で適切な支援を続けることで本人の負担を軽減することもできます。最も大切なことは、家庭と学校が話し合うことにより共通理解し、一番の支援者となることです。
ディスレクシアの指導について
ディスレクシアの指導は、通級指導教室で受けることができます。 通級指導教室とは、大部分の授業を小・中学校の通常の学級で受けながら、一部、障がいに応じた特別な指導を特別な場(通級指導教室)で受ける指導形態で、障がいによる学習上又は生活上の困難を改善し、又は克服するため、特別支援学校学習指導要領の「自立活動」に相当する指導を行います。 宇土市では、宇土小学校、花園小学校、走潟小学校、宇土東小学校、鶴城中学校に通級指導教室が設置されています。
通級指導教室の希望や申込は在籍している学校になります。まずは在籍校にご相談ください。