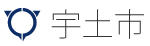学校における食物アレルギーの対応について
近年、特定の食物を摂取することによってアレルギー反応を起こす児童生徒が増加傾向にあることから、国は、食物アレルギー等のある児童・生徒に対しては、校内において校長、学級担任、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員、学校医等による指導体制を整備し、保護者や主治医との連携を図りつつ、可能な限り、個々の児童生徒の状況に応じた対応に努めるよう指導を行っています。従って、本市の学校給食においても、幼稚園を含め食物アレルギーを有する園児・児童・生徒(以下「児童生徒等」)への個別対応が求められてきています。
現在、本市学校給食センターにおいては、食物アレルギーの対応として詳細な献立表の配布、牛乳停止、パン停止、調理を伴わない個食品の代替食の提供(平成29年9月から開始)、原因食材を取り除いた除去食の提供(令和元年12月から開始)を行っているとともに、令和4年1月からは、調理を伴う代替食(揚げ物や焼き物等)の提供をする運びとなりました。
しかし、学校給食の提供においては、集団給食という性質上、対応困難な食材や調理場の施設設備・人員等に限りがあるため、食物アレルギーを有するすべての児童生徒等の様々なケースに対応できない場合があります。
今後とも、国や県、本市の食物アレルギー対応の基本方針に基づき、児童生徒等の安全性を優先し、できる範囲の中で最善の対応に努めていきます。
宇土市食物アレルギー対応の基本方針
- 基本方針1 食物アレルギーを有する児童生徒等の実態を把握し、緊急時の対処について認識する
- 基本方針2 保護者からの要望に応じて詳細な献立表を作成し、適切な対応を行う
- 基本方針3 除去食や代替食の提供は、安全な給食の提供が可能と判断した場合に提供することとする
- 基本方針4 食物アレルギー対応食の提供に関しては、安全性確保のため、原因食物の完全除去対応を原則とする
- 基本方針5 食物アレルギー対応に関しては、「学校生活指導管理表」の提出を必須とする
- 基本方針6 食物アレルギー対応委員会等を校内に設置し、児童生徒等の食物アレルギーに関する情報を集約するなど組織的に対応する